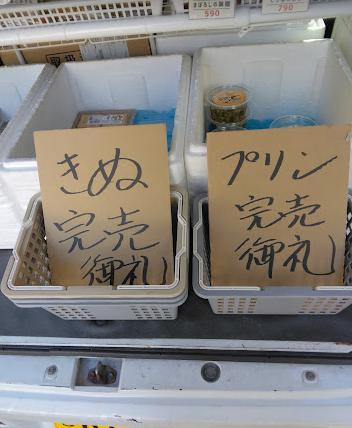豆腐に限らず移動販売での事業は儲からない!と言われています。店舗販売に比較しても、周りの声も厳しいものがあります
果たして本当に移動販売は儲からないのか?
また移動販売を実際に開業している人の平均年収と成功している人の特徴を深堀していきます
移動販売が儲からないと言われる理由
移動販売が「儲からない」と言われる背景には、いくつかの要因が考えられます。これらを理解し、対策を講じることが成功への第一歩となります。
初期投資とランニングコストの負担
車両購入・改造費: 移動販売を始めるにあたり、まず必要となるのが車両です。新車であれば数百万円、中古車でも状態や改造内容によっては高額になることがあります。特に、キッチンカーのように厨房設備が必要な場合は、改造費もかさみます。これらの初期投資を回収するまでに時間がかかり、利益を圧迫する要因となります。
維持費: 車両の維持には、ガソリン代、駐車場代、車検代、保険料などが継続的にかかります。これらのランニングコストも無視できません。
仕入れコスト: 販売する商品にもよりますが、食材や商品の仕入れコストも重要な要素です。天候や季節による価格変動も考慮に入れる必要があります。
出店料: イベントや商業施設の敷地内で営業する場合、出店料が発生することがあります。集客力のある場所ほど高額になる傾向があり、売上とのバランスを考える必要があります。
集客の難しさ
この集客の難しさが移動販売の成功は難しいと言われる最大の理由だと個人的には考えています。ただ、下記を、しっかりと考えて戦略を練り実践していけば移動販売でも勝ち残ることは可能です
出店場所の確保: 移動販売の成否は、出店場所の選定に大きく左右されます。人通りの多い場所やターゲット層が集まる場所を確保することが重要ですが、競合も多く、好条件の場所を見つけるのは容易ではありません。
天候への依存: 屋外での販売が中心となるため、天候に大きく影響されます。雨天や荒天時には客足が遠のき、売上が大幅に減少するリスクがあります。
認知度向上: 実店舗を持たないため、認知度を上げるための工夫が必要です。SNSの活用やチラシ配布など、積極的な広報活動が求められます。
労働集約型のビジネスモデル
長時間労働: 仕込み、移動、販売、片付けと、移動販売は労働時間が長くなりがちです。特に一人で運営している場合、体力的な負担も大きくなります。
体調管理の重要性: 体調を崩すと営業ができなくなり、収入が途絶えてしまうリスクがあります。自己管理が非常に重要です。
競合の激化
参入障壁が比較的低いとされるため、競合が増えやすい傾向にあります。特に人気の業種やエリアでは、差別化を図らないと埋もれてしまう可能性があります。
同様の商品やサービスを提供する店舗との価格競争に巻き込まれることもあります。
許認可や法律の複雑さ
移動販売を行うには、食品衛生責任者の資格取得や保健所の営業許可など、様々な許認可が必要です。また、出店場所によっては道路使用許可なども必要になる場合があります。
これらの手続きが煩雑で、開業までに時間がかかることもあります。
これらの理由から、移動販売は安易に儲かるとは言えない側面があります。しかし、これらの課題を克服し、工夫を凝らすことで成功している方も多くおられます
移動販売している人の平均年収
移動販売を行っている人の平均年収を一概に示すことは非常に難しいです。なぜなら、取り扱う商品、営業日数、出店場所、経営規模(個人か法人か、複数台運営かなど)、経営スキルなど、多くの要因によって収入が大きく変動するためです。
一般的に、個人で運営している場合の年収は、200万円~500万円程度がボリュームゾーンと言われています。しかし、これはあくまで目安であり、これよりも低い場合もあれば、工夫次第で年収1000万円を超えるような成功事例も存在します。
低収入のケース:
集客がうまくいかず、売上が伸び悩んでいる。
経費の管理が甘く、利益率が低い。
営業日数が少ない、または天候に左右されやすい。
単価の低い商品を扱っており、薄利多売になっている。
高収入のケース:
独自の強みや人気メニューがあり、リピーターが多い。
SNSなどを活用した集客が上手い。
イベント出店などで高単価・高回転を実現している。
複数の車両を運営し、事業を拡大している。
経費削減や効率的な運営を徹底している。
重要なのは、平均年収に一喜一憂するのではなく、自身の事業計画をしっかりと立て、目標とする収入を得るためにどのような戦略を取るかを考えることです。
移動販売で成功している人の特徴
移動販売で成功を収めている人たちには、いくつかの共通した特徴が見られます。これらの特徴を参考に、自身のビジネスモデルを構築していくことが重要です。
明確なコンセプトとターゲット設定
「何を」「誰に」「どのように」売るのかというコンセプトが明確です。単に流行っているからという理由で始めるのではなく、自身の強みや情熱を活かせる分野を選んでいます。
ターゲット顧客を具体的に設定し、そのターゲットに響く商品やサービス、店舗デザイン、接客を心掛けています。
独自性と高い商品力
他店にはないオリジナリティあふれる商品や、味や品質に徹底的にこだわった商品を提供しています。
見た目のインパクトや、ストーリー性のある商品開発も成功の鍵となります。
リピーターを生むための工夫(限定メニュー、ポイントカードなど)も積極的に行っています。
戦略的な出店場所の選定と交渉力
ターゲット顧客が集まる場所や、競合が少ない場所をリサーチし、戦略的に出店場所を選んでいます。
イベント主催者や土地の管理者と良好な関係を築き、有利な条件で出店できるよう交渉しています。
曜日や時間帯によって出店場所を変えるなど、フットワークの軽さも武器になります。
集客とマーケティングの巧みさ
SNS(Instagram、X(旧Twitter)、Facebookなど)を積極的に活用し、店舗の魅力や出店情報を発信しています。写真映えする商品の投稿や、フォロワーとのコミュニケーションを大切にしています。
口コミや紹介を生むような仕掛け作りも上手です。
地域のイベントに積極的に参加し、認知度向上に努めています。
徹底した衛生管理と顧客対応
食品を扱う場合、衛生管理は最も重要です。清潔な厨房設備、食材の適切な管理、調理時の衛生対策などを徹底しています。
顧客一人ひとりに対する丁寧な接客やコミュニケーションを大切にし、ファンを増やしています。
お客様からの意見や要望を真摯に受け止め、改善に繋げています。
経営者としての視点と継続的な努力
単に「美味しいものを作る」「好きなものを売る」だけでなく、売上管理、経費管理、利益計算など、経営者としての視点を持っています。
常に新しい情報を収集し、トレンドを把握し、商品やサービスの改善を怠りません。
失敗を恐れず、試行錯誤を繰り返しながら、粘り強く事業を継続しています。
体力と精神力
前述の通り、移動販売は体力勝負の側面があります。また、天候や売上に一喜一憂せず、前向きに事業に取り組む精神力も不可欠です。
これらの特徴は、一朝一夕に身につくものではありません。しかし、意識して取り組むことで、成功の確率は格段に高まるでしょう。
今後の移動販売の展望
移動販売の市場は、今後も一定の成長が見込まれると考えられます。その背景には、いくつかの社会的な変化やニーズの高まりがあります。
多様化するライフスタイルと消費者ニーズ
共働き世帯の増加や単身世帯の増加に伴い、手軽に美味しいものを食べたいという中食・外食ニーズが高まっています。
消費者の嗜好は多様化しており、画一的な店舗よりも、個性的な移動販売の店舗に魅力を感じる層が増えています。
イベントやフェスティバル文化の定着も、移動販売の活躍の場を広げています。
テクノロジーの進化と活用
SNSの普及により、個人でも容易に情報発信ができ、集客に繋げやすくなっています。
キャッシュレス決済の導入は、会計の効率化や顧客の利便性向上に繋がり、売上増加に貢献する可能性があります。
位置情報サービスを活用した出店情報のリアルタイム発信や、オンラインでの事前注文システムなども広がりを見せています。
地域活性化への貢献
過疎地域や買い物難民が発生している地域において、移動販売は生活を支える重要な役割を担うことができます。
地域のイベントと連携することで、賑わいを創出し、地域活性化に貢献する事例も増えています。
地方自治体が移動販売を誘致し、支援する動きも見られます。
サステナビリティへの意識の高まり
地元の食材を活用したり、フードロス削減に取り組んだりするなど、環境や社会に配慮した移動販売は、消費者の共感を呼び、支持される可能性があります。
環境負荷の少ない車両(電気自動車など)の導入も、今後のトレンドとなるかもしれません。
課題と注意点
競争激化への対応: 参入者が増える中で、いかに差別化を図り、独自の価値を提供できるかが重要になります。
法規制の変化への対応: 出店場所に関する規制や衛生管理基準など、関連法規の変更に注意を払い、適切に対応する必要があります。
人材確保と育成: 事業を拡大していく上で、信頼できるスタッフの確保や育成が課題となる場合があります。
移動販売で成功するためのポイント
ニッチ市場の開拓: 大手が参入しにくいニッチな分野や、特定の趣味・嗜好を持つ層をターゲットにした移動販売は、競争を避けやすく、独自のポジションを築ける可能性があります。
異業種との連携: 例えば、書店とカフェ、雑貨店とスイーツなど、異なる業種の移動販売が連携することで、新たな顧客層を開拓したり、相乗効果を生み出したりすることが期待できます。
体験型サービスの提供: 単に商品を販売するだけでなく、調理体験やワークショップなどを組み合わせることで、顧客満足度を高め、付加価値を提供できます。
データに基づいた経営: 売上データや顧客データを分析し、商品開発や出店戦略に活かすことで、より効率的で効果的な経営が可能になります。
まとめ
移動販売は、初期投資を抑えつつ、自由な発想で事業を展開できる魅力的なビジネスです。また私が豆腐の移動販売をしていて一番魅力的に感じているのは、「攻めの商売」が出来るところです。
エリアにしても時間帯にしても自分から攻めて行けるのは最大の魅力です。特にエリアを自由に変更して攻めていけるのは移動販売の魅力でもあり、この点が成功の鍵を握ります。
豆腐だけではなく移動販売での開業には夢があります。その夢を現実にするか、否かは事業主である、あなたの覚悟を戦略・実行力に掛かっています