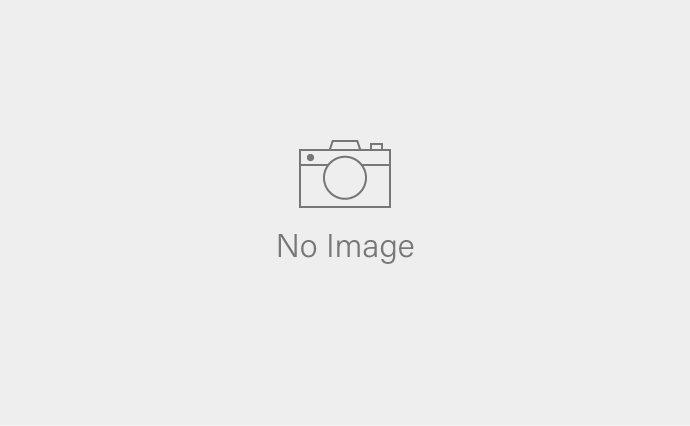移動販売スーパー「とくし丸」での開業を考えている人も居ると思います
とくし丸は、買い物難民が増加する現代において、地域社会に貢献できる非常に意義のあるビジネスモデルです。しかしながら、インターネット上では様々な声が聞かれ、不安を感じることも多いですよね
ここでは、心配される「開業資金の目安と条件」「とくし丸は儲からないのか」「オーナーの平均年収」「辞めたいとのオーナーの声が多い」「『うるさい』との苦情が多い」という項目について、集めた情報を基に詳しく解説し、独立開業の判断材料としていただければ幸いです。
とくし丸の開業資金
とくし丸で独立開業する際には、いくつかの初期費用と継続的な費用が発生します。また、契約にあたっての条件も存在します。
1-1. 開業資金の目安
開業資金は、契約するスーパーマーケットや車両の準備方法によって変動しますが、一般的に250万円~400万円程度が目安とされています。主な内訳は以下の通りです。
加盟金・保証金:
多くのフランチャイズビジネスと同様に、とくし丸でも加盟金や保証金が必要となる場合があります。金額は契約する提携スーパーによって異なるため、個別の確認が必要です。一般的には数十万円から100万円程度が相場と言われています。
車両購入・改造費:
とくし丸の移動販売には専用の軽トラックが必要です。新車で購入する場合、冷蔵設備などの改造費を含めて200万円~300万円程度かかることが一般的です。中古車を利用したり、リース契約を結んだりすることで初期費用を抑えることも可能です。ただし、中古車の場合はメンテナンス費用がかさむ可能性も考慮に入れる必要があります。
車両には、商品を陳列するための棚や冷蔵・冷凍設備、レジシステムなどが搭載されます。これらの設備費用も車両購入費に含まれることが多いです。
商品仕入れ費用(開業時)
開業当初に販売する商品の仕入れ費用も必要です。取り扱う商品数や種類によって変動しますが、数十万円程度を見込んでおくと良いでしょう。とくし丸のビジネスモデルでは、提携スーパーから商品を仕入れる形になるため、在庫リスクは比較的低いと言えます。
その他諸経費:
営業許可の取得費用、保険料(自動車保険、PL保険など)、販売促進費用(チラシ作成など)、運転資金なども考慮しておく必要があります。
1-2. 契約条件
とくし丸の販売パートナー(オーナー)になるための主な条件は以下の通りです。
提携スーパーとの契約:
とくし丸は、本部が直接オーナーと契約するのではなく、地域のスーパーマーケットがとくし丸本部と契約し、そのスーパーマーケットがオーナーと業務委託契約を結ぶ形が一般的です。そのため、開業を希望する地域でとくし丸と提携しているスーパーを探す必要があります。
販売エリア:
販売エリアは提携スーパーとの協議によって決定されます。基本的には、そのスーパーの商圏内で、かつ買い物に困っている高齢者などが多く住む地域が選定されます。
研修制度:
開業前には、とくし丸本部や提携スーパーによる研修が行われます。接客方法、商品知識、車両の運転・管理、販売ルートの構築方法などを学びます。
ロイヤリティ・手数料:
売上に対して一定のロイヤリティや手数料が発生します。これも提携スーパーとの契約内容によって異なりますが、一般的には売上の10%~15%程度と言われています。
オーナーの粗利は、販売価格から仕入れ値を引いた額から、この手数料を差し引いたものになります。販売価格には、スーパーの店頭価格に1品あたり10円~20円程度の上乗せが認められているケースが多いです。
契約期間:
契約期間は通常1年~数年単位で設定され、問題がなければ更新されることが一般的です。
1-3. 必要な資格・スキル
普通自動車運転免許(AT限定可の場合もあり): 軽トラックを運転するため必須です。
コミュニケーション能力: お客様の多くは高齢者であり、日々の会話や安否確認も重要な役割となるため、高いコミュニケーション能力が求められます。
体力: 商品の積み下ろしや長時間の運転、天候に左右される屋外での販売活動など、体力的にタフさが求められる仕事です。
商売感覚・経営努力: 個人事業主として、売上を上げるための工夫や経費管理、顧客開拓などの努力が不可欠です。
とくし丸は儲からないのか?
「とくし丸は儲からない」という声は確かに存在します。
しかし、一概にそうとは言えません。収益性は様々な要因に左右されます。
2-1. 収益構造の基本
とくし丸のオーナーの主な収入源は、商品を販売した際の販売手数料(粗利)です。
販売価格設定: 通常、提携スーパーの店頭価格に、1商品あたり10円~20円程度を上乗せして販売することが認められています。この上乗せ分がオーナーの利益の一部となります。
仕入れ: 商品は提携スーパーから仕入れます。仕入れ価格はスーパーとの契約によります。
販売手数料(ロイヤリティ): 売上の中から、提携スーパーに対して一定の割合の手数料を支払います。
2-2. 「儲からない」と言われる理由
初期投資の回収: 前述の通り、開業にはある程度の初期投資が必要です。この投資額を早期に回収できるかどうかは、その後の収益に大きく影響します。
売上規模の限界: 軽トラック1台でカバーできる範囲や販売できる商品量には限りがあります。そのため、爆発的に大きな売上を上げるのは難しいビジネスモデルと言えます。
経費負担: 車両の維持費(ガソリン代、駐車場代、車検代、修理費など)、保険料、消耗品費などが継続的にかかります。これらを差し引くと、手元に残る利益は思ったより少ないと感じる場合があります。
天候の影響: 雨や雪、猛暑などの悪天候は、客足や自身の体調に影響し、売上が不安定になることがあります。
競合の存在: 地域によっては、他の移動販売やネットスーパー、生協の宅配などとの競合が発生する可能性があります。
体力的な負担: 長時間労働や商品の積み下ろしは体力を消耗し、継続が難しくなるケースもあります。
販売努力の差: 安定した顧客を確保し、売上を伸ばすためには、きめ細やかな顧客対応やルート開拓、品揃えの工夫など、オーナー自身の努力が不可欠です。これが不足すると収益は伸び悩みます。
2-3. 儲けるためのポイント
一方で、安定した収益を上げているオーナーも多数存在します。成功しているオーナーは以下のような工夫をしています。
顧客との信頼関係構築: 定期的な訪問とコミュニケーションを通じて、顧客のニーズを把握し、御用聞きや安否確認といった付加価値を提供することで、固定客を増やしています。
効率的な販売ルートの確立: 需要の高い地域や時間帯を分析し、無駄のないルートを設定することで、販売効率を上げています。
品揃えの工夫: 顧客の要望を積極的に取り入れ、季節商品や地域性の高い商品、少量の個包装商品などを揃えることで、満足度を高めています。
経費管理の徹底: 無駄な経費を削減し、利益率を意識した運営を行っています。
地域との連携: 民生委員やケアマネージャーなどと連携し、新たな顧客を紹介してもらうなどの取り組みも有効です。
結論として、とくし丸が「儲かるか儲からないか」は、オーナーの努力や工夫、そして事業を行う地域環境に大きく左右されると言えます。楽して儲かるビジネスではないことは確かですが、地域に貢献しながら安定した収入を得ることは十分に可能です。
オーナーの平均年収
とくし丸オーナーの平均年収について、公式に発表されている具体的な統計データを見つけることは難しいのが現状です。これは、オーナーが個人事業主であり、売上や経費、労働時間などが個々人で大きく異なるためです。
しかし、様々な情報源(オーナーのブログ、フランチャイズ募集情報、業界関係者の話など)を総合すると、年収の目安としては200万円~500万円程度の範囲で語られることが多いようです。
中には、これ以上の収入を得ている成功事例もあれば、運営が軌道に乗らずに苦労しているケースも見受けられます。
3-1. 年収に影響を与える要因
販売日数・時間: 週に何日稼働し、1日に何時間販売活動を行うかによって売上は大きく変動します。
顧客数・客単価: どれだけ多くの固定客を掴み、一人当たりの購入金額を増やせるかが重要です。
販売エリアの特性: 高齢化率が高く、買い物に困っている人が多いエリアほど需要が見込めます。一方で、競合が多いエリアや、所得水準が低いエリアでは厳しい戦いになることもあります。
商品構成と利益率: 利益率の高い商品をうまく販売できるか、廃棄ロスをどれだけ抑えられるかなども影響します。
経費のコントロール: 車両維持費や燃料費、保険料などの経費をいかに効率的に管理するかが手取り額を左右します。
オーナー自身の営業努力と才覚: 新規顧客の開拓、既存顧客へのきめ細やかなサービス提供、効率的なルート設定など、オーナーの手腕が収入に直結します。
3-2. 個人事業主としての手取り
年収とは売上から経費を差し引いた所得を指しますが、そこからさらに国民健康保険料、国民年金保険料、所得税、住民税などが引かれたものが実質的な手取りとなります。
個人事業主であるため、これらの社会保険料や税金の負担も考慮しておく必要があります。
3-3. 収入の安定性
天候や季節、地域のイベントなどによって売上が変動する可能性があり、会社員のような固定給とは異なります。収入の安定性という点では、ある程度のリスクを伴うことを理解しておく必要があります。
とくし丸のビジネスモデルは、大きな利益を追求するというよりも、地域社会への貢献と安定した生活基盤の確立を目指す方に適していると言えるかもしれません。
「辞めたい」とのオーナーの声が多い?
「とくし丸を辞めたい」というオーナーの声がインターネット上で散見されるのは事実です。これにはいくつかの理由が考えられます。
4-1. 労働環境の厳しさ
体力的な負担:
商品の積み下ろし: 毎日、数十種類、数百点の商品を軽トラックに積み込み、販売先で下ろして陳列し、売れ残りをまた積み込むという作業は、想像以上に体力を消耗します。特に腰への負担が大きいという声はよく聞かれます。
長時間の運転と販売: 1日の稼働時間は長く、朝早くから提携スーパーで商品を積み込み、複数の販売ポイントを巡回し、夕方に戻って片付けや事務作業を行うというサイクルになります。天候に関わらず外での作業が基本となるため、夏場の暑さや冬場の寒さも厳しいです。
休日が少ない、取りづらい: お客様は日々の訪問を待っており、特に一人暮らしの高齢者にとっては安否確認の役割も担っているため、定期的に休むことが難しいと感じるオーナーもいます。代わりの運転手を見つけるのも容易ではありません。
孤独感: 基本的に一人で業務を行うため、孤独を感じやすいという声があります。特に開業当初や悩みを抱えた時に、相談相手が少ないと感じることがあるようです。
売上へのプレッシャー: 個人事業主であるため、売上が直接収入に結びつきます。天候不順や顧客の減少などで売上が落ち込むと、精神的なプレッシャーを感じやすくなります。
顧客との人間関係: 多くのお客様とのコミュニケーションはやりがいである一方、時にはクレーム対応や難しい要望に応えなければならないこともあり、ストレスとなる場合があります。
4-2. 収益面での課題
思ったように儲からない: 事前の想定よりも経費がかさんだり、売上が伸び悩んだりして、期待したほどの収入が得られない場合に、継続が困難になることがあります。
初期投資の回収の遅れ: 初期投資の回収に時間がかかり、資金繰りが苦しくなるケースです。
ロイヤリティの負担: 売上に対するロイヤリティが負担となり、利益が圧迫されると感じる人もいます。
4-3. 本部や提携スーパーとの関係
サポート体制への不満: 本部や提携スーパーからのサポートが十分でないと感じたり、経営方針に不満を持ったりするケースも稀にあるようです。
契約条件への不満: 契約更新のタイミングなどで、条件面での折り合いがつかずに辞めるというケースも考えられます。
4-4. その他の理由
健康上の問題: 体力的な負担が原因で体調を崩し、続けられなくなる。
家庭の事情: 家族の介護や転居など、やむを得ない理由で辞めるケースもあります。
他のビジネスへの転身: とくし丸での経験を活かして、別の事業を始める人もいるかもしれません。
ただし、ネガティブな声ばかりではありません。 多くのオーナーが地域社会に貢献できることに大きなやりがいを感じ、顧客との温かい交流を楽しみながら仕事を続けています。
成功しているオーナーは、上記のような課題を克服するための工夫や努力を重ねています。
重要なのは、これらの「辞めたい」という声の背景にある具体的な理由を理解し、自身がそれらの課題にどのように対処できるかを事前にシミュレーションしておくことです。
「うるさい」との苦情が多い?
とくし丸の移動販売では、お客様に到着を知らせるために音楽を流したり、アナウンスを行ったりすることが一般的です。この音楽やアナウンスの音量が原因で、近隣住民から「うるさい」という苦情が寄せられるケースがあるのは事実です。
5-1. 苦情の原因
音楽の音量・選曲:
特に早朝や夜間、住宅が密集している地域などでは、音楽の音量が大きすぎると騒音と捉えられやすいです。
選曲が一部の人にとっては不快に感じられる可能性もゼロではありません。
アナウンスの音量・頻度:
「とくし丸です、移動スーパーがやってきました」といったアナウンスも、音量や頻度、時間帯によっては迷惑だと感じる人がいます。
車両のエンジン音・アイドリング:
販売中のアイドリングストップを徹底していない場合、エンジン音が気になるという声も考えられます。
販売場所:
住宅の窓のすぐそばや、静かに過ごしたい人が多いエリアでの長時間停車・販売は、苦情に繋がりやすい傾向があります。
5-2. 苦情への対応策と予防策
とくし丸本部や提携スーパー、そして各オーナーは、このような苦情に対して以下のような対策を講じています。
音量の調整:
販売エリアの特性(住宅密集地、病院や学校の近くなど)や時間帯に応じて、音楽やアナウンスの音量を細かく調整する。
スピーカーの指向性を考慮し、音が広範囲に拡散しすぎないようにする。
音楽・アナウンスの時間帯への配慮:
早朝や深夜の販売を避ける、または静かなエリアでは音楽を止めて個別に訪問するなど、時間帯に応じた配慮を行う。
事前の周知とコミュニケーション:
販売を開始する前に、近隣住民にチラシを配布するなどして、移動販売の目的や訪問日時、連絡先などを伝え、理解を求める。
苦情があった場合は真摯に受け止め、謝罪するとともに、具体的な改善策(音量を下げる、その場所での音楽を止めるなど)を提示し、実行する。
販売場所の選定:
できるだけ迷惑になりにくい場所を選んで停車する。
自治会や町内会と連携し、販売場所や時間について事前に相談する。
車両のアイドリングストップの徹底: 環境配慮と騒音対策の両面から重要です。
苦情受付窓口の明確化: 提携スーパーやオーナーの連絡先を明示し、何か問題があればすぐに連絡してもらえる体制を整える。
5-3. 地域住民との良好な関係構築の重要性
とくし丸の事業は、地域住民の理解と協力なしには成り立ちません。騒音問題は、その事業の根幹を揺るがしかねない重要な課題です。
メリットの周知: とくし丸が買い物難民の支援や地域の見守りといった社会的な役割を果たしていることを丁寧に説明し、理解を求めることが大切です。
丁寧な対応: 苦情だけでなく、地域住民からの要望や意見にも耳を傾け、可能な範囲で対応することで、信頼関係を築くことができます。
「うるさい」という苦情は、一部の地域や状況で発生する可能性はありますが、多くのオーナーは地域住民への配慮を忘れず、良好な関係を築きながら活動しています。事前の対策と誠実な対応が鍵となります。
まとめ
とくし丸での独立開業は、買い物難民の支援という社会貢献と、自身のビジネスを両立できる可能性を秘めた魅力的な選択肢です。
しかし、本稿で見てきたように、開業資金の準備、収益性の確保、体力的な負担、そして地域住民との関係構築など、乗り越えるべき課題も少なくありません。
開業を成功させるために重要なポイント
十分な情報収集と事業計画: 今回挙げた懸念点以外にも、様々な情報を収集し、自身の状況(資金、体力、適性など)と照らし合わせて、現実的な事業計画を立てることが不可欠です。可能であれば、現役のオーナーに話を聞く機会を設けるのも良いでしょう。
体力と覚悟:
楽な仕事ではありません。体力的な厳しさを理解し、それを乗り越える覚悟と健康管理が求められます。
コミュニケーション能力と人間力: お客様や地域住民との良好な関係を築くことが、事業の安定と成長に繋がります。
提携スーパーとの良好な関係: スムーズな商品供給や経営サポートを受けるためには、提携スーパーとの信頼関係が重要です。
地域への貢献意識: 単に「儲ける」だけでなく、「地域のために何ができるか」という視点を持つことが、やりがいと事業継続のモチベーションに繋がります。
ネガティブな情報に目を向けることも重要ですが、それと同時に、とくし丸が多くの地域で必要とされ、多くのオーナーが顧客からの「ありがとう」を励みに日々活動しているという事実も忘れてはなりません。
ご自身の価値観、体力、経営能力、そしてとくし丸のビジネスモデルへの共感を総合的に検討し、後悔のない決断をすることが大切です
もし可能であれば、一度、ご自身の地域で活動されているとくし丸を見学したり、オーナーにお話を聞いたりする機会を持たれることを強くお勧めします。現場の空気を感じることで、より具体的なイメージが湧き、判断材料が増えるはずです。